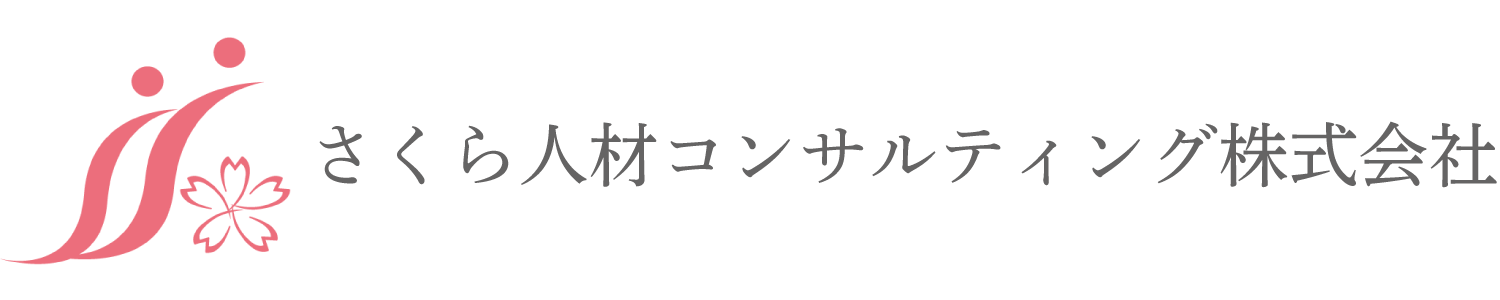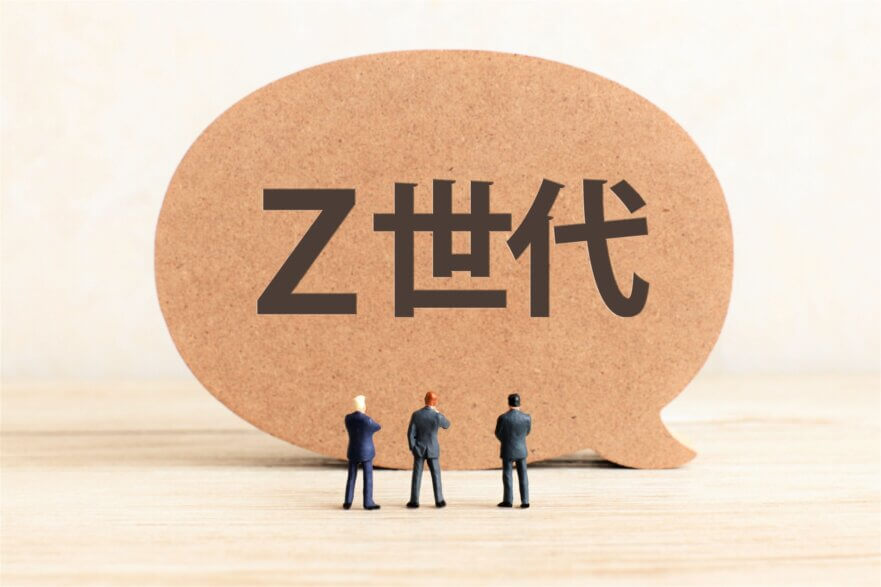
ハラスメントを恐れて“何も言えない上司”が急増中――Z世代に響く伝え方とは?
こんにちは。
さくら人材コンサルティング株式会社の伊藤明美です。
ハラスメント防止が当たり前の時代になり、
研修の現場でも
「部下への声かけが怖い」
「何を言ったらパワハラになるのかわからない」
という声を本当によく耳にします。
特に最近は、指導する立場の上司自身が
「気を使いすぎて疲弊してしまう」ケースが増えています。
かつてのように“叱って育てる”時代ではなくなり、
“伝え方”に細やかな配慮が求められる今。
それでも、上司はチームの成長を支え、
時には厳しいことも伝えなければなりません。
では、どうすればハラスメントを恐れず、
Z世代にも響くマネジメントができるのでしょうか?
今回は、心理学や実際の現場事例を交えながら、
上司の「疲弊しない伝え方」について考えてみたいと思います。
1. 「ハラスメントを恐れて何も言えない上司」が増えている
以前は「部下を叱るのも教育のうち」
と考える風潮がありました。
しかし、働き方改革やコンプライアンス意識の高まりにより、
職場の空気は一変しました。
特に2019年の
「パワーハラスメント防止法(改正労働施策総合推進法)」
施行以降は、上司が部下に対して行う言動に厳しい目が向けられています。
現場では、次のような声が多く聞かれます。
「注意したら泣かれてしまった」
「LINEでの指摘が“圧を感じた”と言われた」
「部下に嫌われたくなくて言えない」
その結果、
「本来伝えるべきことを伝えられない」
「言いたいことを飲み込む」
上司が増えています。
これは、一見“優しい職場”のように見えて、
実はチームの生産性や信頼関係を弱めてしまう大きなリスクでもあります。
2. 背景にあるのは“Z世代”の価値観の変化
Z世代(1990年代後半〜2010年代生まれ)は、
SNSやネット社会と共に育った世代です。
彼らは「個を尊重する」価値観を強く持ち、
上下関係よりも“対等な関係”を求めます。
また、情報リテラシーが高く、
「パワハラ」「モラハラ」といった言葉も自然に使いこなします。
Z世代が仕事で重視するのは「共感」「安心感」「納得感」。
つまり、“なぜその指摘が必要なのか”を
理解できないと受け入れにくいのです。
一方で、上司世代(40〜50代)は
「自分が若いころは厳しく育てられた」経験を持つため、
つい“自分がされた指導”を再現しがちです。
この価値観のギャップが、ハラスメント誤解の温床になります。
3. 「言わない」こともリスクになる
上司が「怖くて何も言えない」状態は、
実はハラスメント防止の観点からも危険です。
なぜなら、「注意・指導しないこと」によって、
次のような副作用が生まれるからです。
- チームのルールが曖昧になり、トラブルが増える
- 頑張る部下が報われず、不公平感が生まれる
- 上司と部下の信頼関係が希薄になる
心理学では、“過剰な優しさ”も一種の攻撃性と捉える考え方があります。
相手を傷つけまいとするあまり、
必要なフィードバックを避けてしまうことは、
相手の成長の機会を奪う行為にもなりかねません。
アドラー心理学では、「課題の分離」という考え方があります。
つまり、“相手の課題”と“自分の課題”を混同しないこと。
部下がどう受け取るかは相手の課題。
上司は、自分の役割として「必要な指導を伝える」ことに
集中すればよいのです。
4. 上司が疲弊する3つのパターン
私の研修現場でも、上司が疲弊してしまう背景には
いくつかの共通パターンがあります。
①「正解探し」に陥るタイプ
「どんな言い方ならパワハラにならないのか?」を
常に探し続け、結局行動できなくなってしまうタイプです。
完璧な言い方を目指すより、
“伝える目的”を明確にすることが大切です。
②「いい人」になりすぎるタイプ
相手に嫌われたくない、波風を立てたくないという気持ちが強く、
注意を避けてしまうタイプ。
フィードバックは“相手の成長支援”と位置づけて、
優しさの意味を見直しましょう。
③「我慢の末に爆発」タイプ
普段は我慢していても、溜め込みすぎて
感情が爆発してしまうタイプ。
日常的なコミュニケーション(マイクロ・フィードバック)で
感情をため込まない習慣を持ちましょう。
5. Z世代に響くマネジメント3つのポイント
① 共感ファースト:「否定」より「理解」から入る
心理学的に、人は“自分を理解してもらえた”
と感じると防衛的になりにくい傾向があります。
いきなり「なんでできないの?」ではなく、
「そのやり方でやってみたんだね」
「まずやってくれたんだね、ありがとう」
といった共感の一言を添えるだけで、相手の受け取り方は変わります。
② 理由をセットで伝える
Z世代は「納得感」を重視します。
「〇〇をやってください」だけではなく、
「なぜそれが必要なのか」を説明することで、
理解度とモチベーションが大きく変わります。
例:
❌「報告はもっと早くして」
⭕「報告が早いとチーム全体が助かるから、
できれば午前中に共有してもらえると嬉しい」
③ 定期的な1on1で“信頼貯金”をつくる
ゴットマン博士の研究では、良好な人間関係を保つためには、
ポジティブな言動:ネガティブな言動=3:1以上が
望ましいとされています。
これは職場にも当てはまります。
日頃から「ありがとう」「助かるよ」といった
ポジティブな言葉を積み重ねておくと、
いざ注意や指導をする場面でも、関係が壊れにくくなります。
6. 伝え方の工夫で「叱る」も「支援」に変わる
叱ることは悪いことではありません。
問題は“叱り方”です。
ポイントは次の3つ。
1️⃣ 行動に焦点を当てる(人格否定はNG)
例:「報告が遅れた」事実を伝える。「あなたはダメだ」は避ける。
2️⃣ タイミングを逃さない
翌日よりも“その場で短く”伝えるほうが効果的。
3️⃣ フォローで終わる
叱って終わりではなく、「次はどうしようか?」と一緒に考える。
こうした対応は、Z世代にとって“支援的関わり”として
受け止められやすくなります。
7. 「心理的安全性」を誤解しない
近年よく聞かれる「心理的安全性」。
これは「何を言っても怒られない職場」ではなく、
「意見を言っても不当な扱いを受けない職場」を意味します。
心理的安全性が高い職場とは、
建設的な意見やミスの共有ができる環境のこと。
そのためには、上司が部下に“安心して
話せる雰囲気”を作ることが重要です。
しかし、“優しさ一辺倒”では安全性は育ちません。
時には厳しい話もしながら、それでも関係を維持できる職場
――それが本当の心理的安全性です。
8. 事例紹介:「怒らない上司」と「伝える上司」の違い
ある企業の例です。
A上司は「パワハラが怖い」と言って、
部下のミスを指摘せず、結局クレームが発生しました。
一方、B上司はミスがあった際にこう伝えました。
「今回は確認が抜けていたね。でも、対応スピードはすごくよかった。
次はこのチェックリストを一緒に使ってみようか。」
結果、部下は「注意されたけど、信頼されていると感じた」
と話していました。
違いは、“人格”を否定せず、
“行動”を指摘し、“改善策”を共有したこと。
これがまさに、
アサーティブ(自分も相手も大切にする)コミュニケーションの実践です。
9. 上司自身のメンタルケアも忘れずに
指導に気を使いすぎて疲弊している上司は、本当に多いです。
自分の感情を抑え込み続けると、ストレスが蓄積し、
心身の不調につながることもあります。
まずは、「上司も人間である」ことを忘れないでください。
完璧を求めすぎず、悩んだら同僚や人事に相談する。
上司同士で支え合う文化が、職場の健全さを保ちます。
10. まとめ:「伝え方を恐れず、関わり方を磨く」
ハラスメントを恐れて“何も言えない上司”が増えているのは、
時代の流れの中で自然なことかもしれません。
けれども、「伝えること」自体をやめてしまうと、
職場の成長は止まってしまいます。
Z世代に響くのは、“上からの命令”ではなく、
“共に考える姿勢”。
そして、上司の言葉に“誠実さ”と“目的意識”があれば、
必ず伝わります。
最後に、私が研修でよくお伝えしている言葉を紹介します。
「ハラスメントを恐れるより、
“誤解されない関わり方”を身につけよう」
伝え方を磨くことは、部下を守るだけでなく、
上司自身を守ることにもつながります。
ぜひ、“叱る勇気”と“支える優しさ”の両立を目指していきましょう。
さくら人材コンサルティングの研修サービスはコチラです!
さくら人材コンサルティング研修サービスコンテンツ
さくら人材コンサルティング株式会社
東京都港区浜松町2-2-15 ダイヤビル2F
営業時間:平日9時~18時
電話番号:03-6868-3248