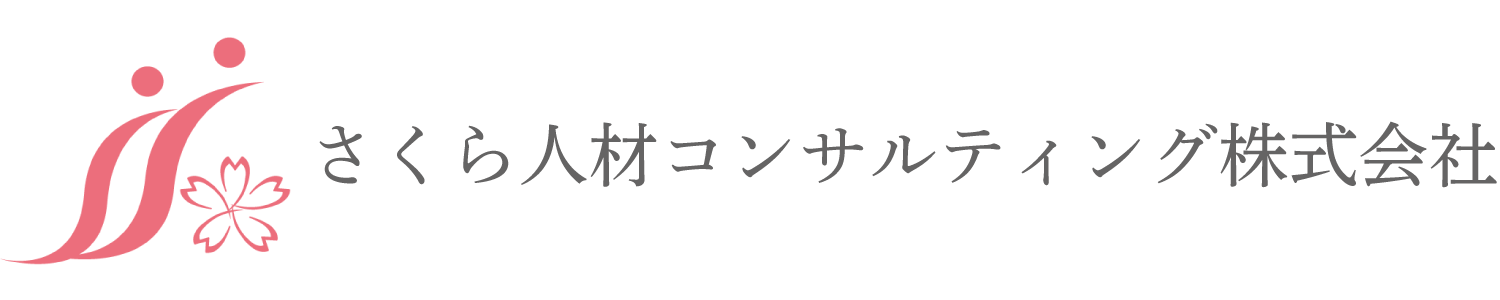「相談される上司」と「相談されない上司」の違いとは?
こんにちは。
さくら人材コンサルティング株式会社の伊藤明美です。
■はじめに:なぜ、部下は上司に相談しなくなったのか
近年、管理職の方からこんな声をよく聞きます。
「部下が何を考えているのかわからない」
「悩みがあっても話してもらえない」
「最近の若手は、どう関わっていいのかわからない」
同じ職場・同じチームでも、
なぜか自然と部下が集まる上司と、
そうでない上司がいます。
この違いは、決して「性格」や「人柄」
だけではありません。
実は、“相談しやすさ”には心理学的な要因と
日々のコミュニケーション習慣が
深く関係しています。
今回は、心理学の観点から
「この人には話しても大丈夫」と感じさせる上司の特徴を
4つのポイントに分けて整理します。
1. 「すぐ答えを出さない」上司は信頼される
相談しやすい上司の最大の特徴は、
“話を聴いてくれる”感覚を与えることです。
多くの上司は、相談を受けると
「解決策を出してあげなければ」と思いがちです。
しかし、人はアドバイスよりも、まず
「理解してもらえた」と感じることで安心します。
共感的理解とは何か心理学ではこれを
「共感的理解(Empathic Understanding)」と呼びます。
アメリカの心理学者カール・ロジャーズはこう言いました。
「相手を変えようとする前に、
相手の世界を理解しようとする姿勢こそが、
人を成長させる。」
部下が求めているのは、答えよりも“共感”です。
「あなたの気持ちを受け止めています」
という姿勢が信頼につながります。
■実践例:「一緒に考える」上司
たとえば、部下が「お客様対応がうまくいかない」と
相談してきた場合。
すぐに「こうすればいい」と言うのではなく、
こう問いかけてみましょう。
「どんな場面で難しさを感じた?」
「自分なりにどう対処しようと思っている?」
上司が結論を出すのではなく、
部下と一緒に考える姿勢を見せる。
それだけで、部下は「この人なら話しても大丈夫」
と感じます。
2. 「普段から雑談できる関係」をつくっている
相談しやすい上司は、日常の小さな会話を大切にしています。
「最近どう?」「この前の提案、良かったね」といった
業務に関係ない雑談が、心理的距離を近づけます。
雑談は「信頼残高」を貯める行為
アドラー心理学では、人間関係の基本は「横の関係」だといわれます。
上司と部下という“縦の関係”の中でも、
対等な人間として尊重し合える「横の感覚」を持つことが重要です。
雑談とは、まさにその“横の関係”をつくる土台。
雑談が多い職場ほど、困ったときに助け合える文化が育ちます。
■雑談が苦手な人へのヒント
「何を話せばいいかわからない」という方は、
“相手の変化に気づく”ことから始めてみましょう。
- 髪型が変わった
- いつもより元気がない
- 新しい文房具を使っている
このような小さな変化に気づいて声をかけるだけで、
「見てくれている」というメッセージになります。
雑談とは、関心の表現。
“あなたに興味があります”というサインなのです。
3. 「表情・トーン・沈黙」に安心感がある
相談のしやすさは、言葉よりも非言語的な印象に
大きく左右されます。
「何を言うか」よりも「どう言うか」が重要です。
■非言語の力:表情とトーン
心理学のメラビアンの法則では、
コミュニケーションの影響度は以下の通りです。
- 言語情報(言葉の内容):7%
- 聴覚情報(声のトーン・速さ):38%
- 視覚情報(表情・姿勢・仕草):55%
つまり、表情とトーンが93%を占めているということ。
上司が穏やかなトーンで話すだけで、
部下の安心感は格段に高まります。
■脳科学的には「ミラーニューロン」が影響
脳には、相手の表情や感情を“写し取る”働きを持つ
「ミラーニューロン」という神経細胞があります。
上司が焦っていれば、部下も焦り、
上司が穏やかでいれば、部下も穏やかになります。
つまり、「上司の感情がチームの空気をつくる」のです。
■沈黙の持つ力
多くの人は沈黙を“気まずい時間”と感じます。
しかし、相談の場における沈黙は、相手が考えているサイン。
上司がその沈黙に耐え、落ち着いて見守ることで、
「この人は急かさない」「自分のペースを尊重してくれる」
という安心感を生みます。
“沈黙に寄り添う”のも立派なコミュニケーションです。
4. 「話したあと、気持ちが軽くなる」上司
本当に相談しやすい上司とは、
話し終えた部下が「すっきりした」「話してよかった」
と感じる人です。
否定や評価ではなく「受容の言葉」を
部下が話した後に、
「それは甘いよ」「そんなの当たり前」と返してしまうと、
せっかくの勇気が潰されてしまいます。
代わりに、こんな言葉を使ってみましょう。
「そう感じたんだね」
「大変だったね」
「話してくれてありがとう」
このような“受け止める言葉”は、
部下の気持ちを整理させ、心理的安全性を高めます。
■心理的安全性とは
ハーバード大学のエイミー・エドモンドソン教授は、
心理的安全性を次のように定義しています。
「率直に意見を言っても、罰せられたり
恥をかかされたりしないと信じられる状態」
つまり、「この人の前なら本音が言える」と思える雰囲気。
相談しやすい上司は、この空気を日々つくっています。
Googleの研究プロジェクト「Aristotle」でも、
心理的安全性の高いチームほど生産性が高く、
離職率が低いことが分かっています。
5. 実際の現場で起きた“相談されない上司”の事例
ある製造業の課長Aさん。
部下から“話しかけづらい上司”として知られていました。
Aさん本人は「自分はフラットだ」と思っていましたが、
部下は「話しかけても聞いてくれない」と感じていました。
原因は、Aさんが常にパソコンを見ながら返事をしていたこと。
「ながら対応」が“壁”をつくっていたのです。
■小さな行動の変化が信頼を生む
Aさんは、部下から話しかけられたときに
「手を止めて、相手の目を見る」ことを意識しました。
それだけで、職場の空気が変わりました。
数か月後には、「話しやすくなった」という声が増えたそうです。
相談しやすさは、“性格”ではなく“行動習慣”。
意識を変えれば、誰でも身につけることができます。
6. 相談される上司が持つ「4つの力」
| 特徴 | 心理的要素 | キーワード |
| 1. すぐ答えを出さない | 共感的理解 | 傾聴・共感 |
| 2. 雑談を大切にする | 横の関係 | 信頼残高 |
| 3. 表情・トーン・沈黙に安心感 | 非言語コミュニケーション | ミラーニューロン |
| 4. 話した後に気持ちが軽くなる | 心理的安全性 | 受容・承認 |
7. 「相談しやすさ」はマネジメントの力
部下が安心して話せる環境がある職場は、
トラブルが早期に発見でき、チームの生産性も高まります。
つまり、“相談しやすさ”は組織のリスク管理であり、
最も効果的な離職防止策でもあるのです。
8. まとめ:「相談される上司」は、心の余白を持っている
相談される上司とは、特別なスキルを持つ人ではありません。
相手の気持ちを尊重し、
理解しようとする“心の余白”を持った人です。
- 答えを急がずに聴く
- 日常の雑談を大切にする
- 穏やかな表情で迎える
- 否定せず受け止める
これらを実践することで、
部下は自然と心を開き、組織の信頼関係が深まります。
■おわりに
上司の「ひとこと」「表情」「間」の取り方が、
部下の安心とモチベーションを左右します。
ハラスメント防止やメンタル不調対策も、
実は“相談しやすい関係づくり”から始まります。
今日の職場で、ぜひ一つでも実践してみてください。
きっと、部下の反応が少しずつ変わっていくはずです。
さくら人材コンサルティングの研修サービスはコチラです!
さくら人材コンサルティング研修サービスコンテンツ
さくら人材コンサルティング株式会社
東京都港区浜松町2-2-15 ダイヤビル2F
営業時間:平日9時~18時
電話番号:03-6868-3248