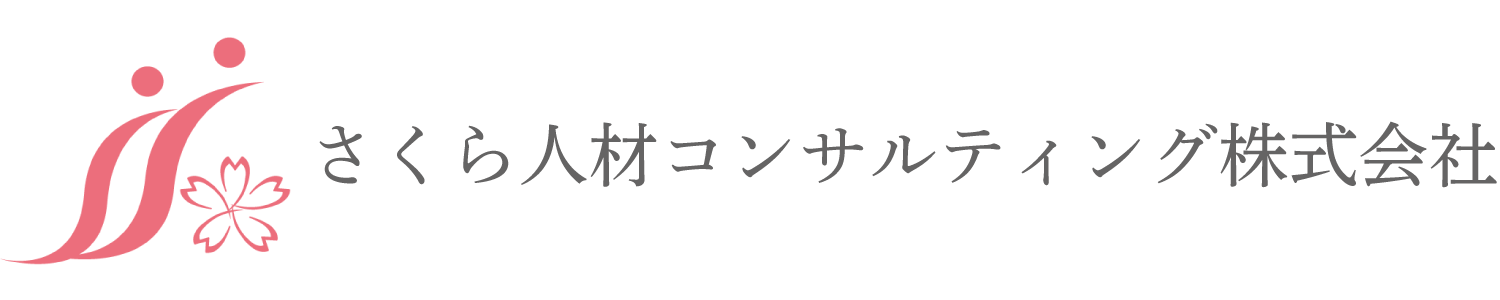近年増えている「ホワイトハラスメント」とは? 〜善意が職場を追い詰める時代〜
はじめに
近年、「ハラスメント」という言葉は
私たちの職場や日常生活において
もはや避けて通れないテーマになっています。
パワハラ、セクハラ、マタニティハラスメントなど、
すでに多くの種類が認知され、
社会的な問題として議論されてきました。
その一方で、比較的新しい概念として
注目を集めているのが 「ホワイトハラスメント」 です。
これは一見「善意」や「配慮」の形を取りながらも
相手を追い詰めてしまう行為を指します。
たとえば、
- 「残業は禁止だから、どんなに仕事が残っていても帰りなさい」
- 「有給は必ず全員が消化すべきだ。体調が悪くなくてもとにかく休みなさい」
- 「ハラスメントにならないように一切指導はしない」
こうした行為は一見「ホワイト=正しい、清い」ように見えますが
実際には職場の柔軟性を奪い、現場の社員にとっては
逆に大きなストレス源となるのです。
本記事では、この「ホワイトハラスメント」という現象が
なぜ生まれ、どのような問題を引き起こしているのかを掘り下げます。
そして心理学的な背景や、職場でできる予防策・対応策についても
具体的にご紹介して参ります。
1. ホワイトハラスメントとは何か
1-1 定義
「ホワイトハラスメント」という言葉には
明確な法律上の定義はまだありません。
一般的には次のように説明されます。
善意や配慮、ルール遵守の押し付けが、かえって相手を苦しめる行為
つまり「悪意ではなく善意」がベースになっている点が特徴です。
従来のパワハラのように「叱責・罵倒・暴力」といった
露骨な攻撃性はなく、むしろ「良かれと思って」が前面に出ています。
1-2 具体例
- 働き方改革の行き過ぎ
→「残業禁止」の一律ルールで、家庭の事情で残業を希望する人まで帰らされる。 - 休暇取得の強制
→「休まないと評価を下げる」というプレッシャーで、かえって休みにくくなる。 - 指導回避型のマネジメント
→「厳しく言うとパワハラになる」と指導しなくなる結果、若手が育たない。 - 過剰な配慮
→「女性だから軽い仕事を」「新人だから大事な仕事は任せない」などの“優しさ”。
こうした行為は「善意」という衣をまとっているために
指摘や改善が難しいのです。
2. なぜホワイトハラスメントが増えているのか
2-1 社会背景
- 働き方改革とハラスメント防止法制の広がり
企業はコンプライアンス遵守の姿勢を強め、ハラスメントを恐れるあまり
「過剰防衛」に走る傾向があります。 - SNSによる拡散リスク
一言の叱責や対応がSNSで拡散され「炎上」する可能性があるため
企業や管理職が極端に安全策を取ろうとします。 - 多様性の重視
ダイバーシティの推進は重要ですが、それが「一律の平等」や
「過度な配慮」にすり替わることで、本来の柔軟性が失われています。
2-2 心理学的背景
心理学の観点からは、以下の要因が挙げられます。
- 過剰適応
周囲から「よい人」「模範的な管理職」であろうとするあまり
相手に必要以上に配慮し、結果的に抑圧的になる。 - 認知の歪み
「指導=パワハラ」「残業=悪」といった白黒思考が働き
中間的な柔軟対応ができなくなる。 - 同調圧力
「会社の方針だから」「みんな休んでいるから」という集団の圧力が
個人の自由を奪う。
3. ホワイトハラスメントの実態と事例
ここでは、実際に報告されている事例をいくつか紹介します。
事例1:新人指導ができない職場
ある企業では、若手社員が失敗を繰り返しても
「厳しく言うとパワハラになるから」と上司は叱責を避けました。
その結果、成長機会を失った若手が自信をなくし
早期離職につながってしまいました。
事例2:有給取得の“強制”
「会社の方針で必ず有給を消化すること」と義務化された企業。
しかし、繁忙期に強制的に休まされた社員は
業務が滞ることへの不安や、仲間への罪悪感を抱き
かえって休むことがストレスとなっていました。
事例3:残業ゼロの圧力
育児や住宅ローンの関係で「残業代が欲しい」という社員もいる中
会社は「残業は悪だから一律禁止」としました。
結果として、家庭事情に合った働き方ができず、不満を抱く社員が増えました。
4. ホワイトハラスメントがもたらす影響
4-1 組織への影響
- 人材の成長機会を奪う
- 柔軟性を欠いた硬直した組織文化になる
- 「やらされ感」によるモチベーション低下
- 離職率の上昇
4-2 個人への影響
- 過剰なストレスや無力感
- 自己効力感の低下
- 本音を隠して働くことによる心理的疲労
- 「守られすぎる」ことによる依存体質の助長
5. ホワイトハラスメントを防ぐためのポイント
5-1 組織として
- ルールは一律ではなく“原則+例外”で運用する
残業禁止も「原則は禁止。ただし家庭事情など
本人の希望があれば柔軟に対応」など。 - 管理職研修の充実
「指導とパワハラの違い」を学び
適切なフィードバックスキルを身につける。 - 心理的安全性の確保
社員が意見を言いやすい雰囲気をつくり
「配慮が行き過ぎている」と指摘できる職場風土を育む。
5-2 個人として
- 自己主張(アサーション)スキルを磨く
「私はこう働きたい」と自分の希望を伝える力を持つことが重要です。 - 善意の裏側を振り返る
「相手のためにやっているつもりが、相手の自由を奪っていないか?」
と自問する。 - 相談窓口の活用
ホワイトハラスメントは表面化しづらいからこそ
相談の仕組みを活用して声を上げることが必要です。
6. 心理学からみたアプローチ
6-1 アドラー心理学
アドラー心理学では「課題の分離」という考え方があります。
これは「誰の課題かを明確にし、他者の課題に踏み込みすぎない」
というものです。
ホワイトハラスメントは「相手の課題」に過剰に
介入してしまう典型例といえます。
6-2 認知行動療法
「残業=悪」といった極端な思考を修正し
柔軟な認知に切り替えることが求められます。
6-3 アンガーマネジメント
指導やルール運用において「怒りの爆発を避ける」ことだけでなく
「過剰に抑圧する」こともリスクであると認識し
適度な表現を身につけることが有効です。
7. 今後の展望
ホワイトハラスメントは、今後ますます注目されるテーマです。
- 「善意によるハラスメント」への社会的な理解が進む
- 法的なガイドラインや企業マニュアルに取り入れられる可能性
- 働き方改革の第2フェーズとして「柔軟性」「個別最適化」が重視される
まとめ
ホワイトハラスメントは、従来のハラスメントのように
「悪意」からではなく「善意」や「正義感」から生まれる点で
非常にやっかいな問題です。
- 善意が行き過ぎれば、相手の自由や成長を奪う。
- 「一律」「過剰防衛」は、柔軟性を欠き、組織と個人双方に悪影響を与える。
- 心理学的な視点からは「課題の分離」「認知の柔軟性」「適度な自己主張」が解決の鍵になる。
「良かれと思って」が「かえって相手を追い詰める」ことがないように
私たち一人ひとりが配慮と自由のバランスを意識することが大切です。
さくら人材コンサルティングの研修サービスはコチラです!
さくら人材コンサルティング研修サービスコンテンツ
さくら人材コンサルティング株式会社
東京都港区浜松町2-2-15 ダイヤビル2F
営業時間:平日9時~18時
電話番号:03-6868-3248