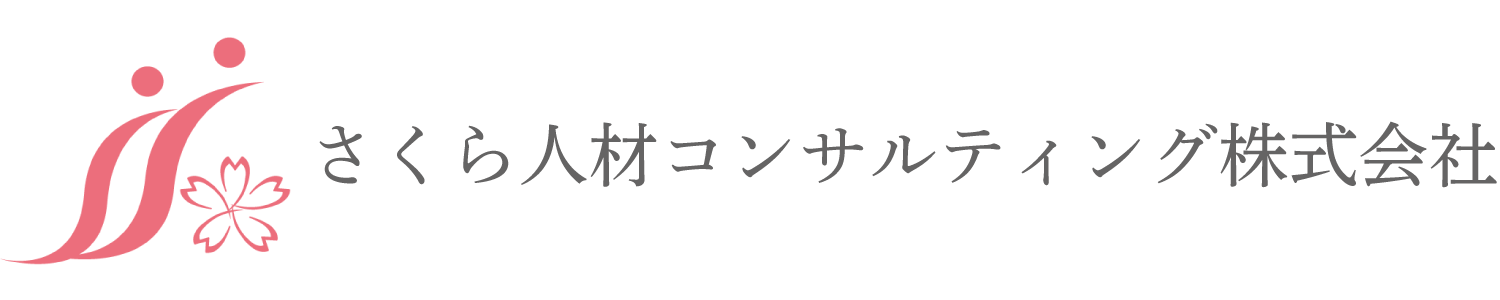「パワハラしているつもりはない」――なぜ本人は自覚できないのか?
こんにちは。
さくら人材コンサルティング株式会社の伊藤明美です。
近年、企業のハラスメント対策は急速に進み、
社内研修や相談窓口の設置も一般的になりました。
それでもなお、ハラスメント相談の現場では
「悪気はなかった」「そんなつもりじゃなかった」
という言葉を耳にします。
つまり、“パワハラをしている本人が自覚していない”
というケースが非常に多いのです。
被害者が深く傷ついている一方で、
加害者は「正しい指導をした」と思い込んでいる。
このギャップこそが、職場の人間関係を複雑にし、
再発防止を難しくしています。
なぜ、人は自分の行動を“ハラスメント”だと
気づけないのか?
そして、どうすればその無自覚に気づけるのか?
今回は、心理学や現場の事例を交えながら、
「パワハラの自覚が生まれないメカニズム」
について掘り下げていきます。
■「悪気がないのに」起きるハラスメント
そんな中で、ハラスメント相談や研修の現場で
非常によく耳にする言葉があります。
「あの人、ちょっと言い方がきついけど、
悪気はないんだよね」
職場に、そんな“悪気のない厳しさ”を持つ人はいませんか?
実は、パワーハラスメント(以下パワハラ)の加害者の多くは、
「自分がハラスメントをしている」という自覚がありません。
むしろ本人は「自分は部下思いだ」と
信じているケースも少なくありません。
それではなぜ、人は“自分がパワハラをしている”ことに
気づけないのでしょうか。
今回は、その心理的なメカニズムを解き明かしていきます。
■1.「指導」と「パワハラ」の境界があいまい
パワハラが発生しやすい職場では、
加害者の多くが「自分は部下を育てようとしている」と
考えています。
特に昭和世代の管理職に多いのが、
「厳しく叱ってこそ教育だ」
という信念です。
彼らが若手だったころは、
「上司の言うことは絶対」「怒られて一人前」
という価値観が一般的でした。
当時は、叱責の背景に“愛情”があると
信じられていたのです。
つまり、本人の中では“正義の行動”なのです。
「部下を甘やかしてはいけない」
「厳しさが本人のためだ」
と思い込んでいる。
しかし、この“善意の指導”が、
受け手にとっては脅威や恐怖として
受け取られることがあります。
この「正義」と「恐怖」のギャップこそが、
パワハラを“無自覚のうちに”引き起こす最大の要因です。
●境界を曖昧にする要因:組織文化と「時代のズレ」
例えば、ある企業では管理職が部下に対して
「なんでこんなこともできないんだ!」と
怒鳴る場面が日常でした。
しかし、若手社員から見るとそれは
「指導」ではなく「攻撃」。
昭和・平成・令和と価値観が変わる中で、
“叱る文化”はすでに“脅す文化”に変わりつつあります。
組織心理学者のエドガー・シャインはこう述べています。
「組織文化は、成功体験を繰り返すことで固定化される」
つまり、かつて「厳しく指導して成果が出た」
経験がある人ほど、
同じやり方を続けようとするのです。
それが時代と合わなくなっても、本人には気づけません。
なぜなら「昔はそれで上手くいった」という
成功体験が根深く残っているからです。
■2.「自分の感情」に鈍感になっている
心理学的にいうと、
自分の感情に気づけない人は、
他者の感情にも気づけません。
これは「アレクシサイミア(感情失認症傾向)」
という心理特性でも説明されます。
感情を言語化したり、表現するのが苦手な人ほど、
自分のイライラや不安、焦りに気づかないまま
行動してしまうのです。
●感情を抑え込む管理職の心理
多くの管理職は、
「弱みを見せてはいけない」
「常に冷静でなければならない」
というプレッシャーを感じています。
そのため、「焦り」「苛立ち」「無力感」
といったネガティブ感情を抑え込みがち。
その抑圧された感情が、
ある瞬間に攻撃的な言葉や態度として
漏れ出すことがあります。
たとえば、
- 「何度言えばわかるんだ!」
- 「俺の若い頃はもっと大変だった!」
といった言葉は、実は“怒り”ではなく
“無力感”の裏返しであることも多いのです。
●感情マネジメントができないとどうなるか
アンガーマネジメントの観点では、
怒りは「二次感情」と呼ばれます。
その奥には「不安」「寂しさ」「期待外れ」などの
一次感情があります。
その一次感情に気づけないまま指導を行うと、
本来伝えたい内容ではなく、感情が主導してしまう。結果として、パワハラ的な言動になってしまうのです。
■3.「部下が言い返さない」ことが誤解を生む
もう一つの大きな誤解は、
「部下が何も言わない=納得している」と
思い込むことです。
実際には、沈黙の裏に次のような心理が隠れています。
- 「怖くて何も言えない」
- 「どうせ言っても無駄」
- 「反論したら評価が下がる」
つまり、沈黙は“同意”ではなく“諦め”なのです。
しかし、上司は「特に反発されなかった=理解された」
と勘違いする。
こうして、“気づけない構造”が職場に生まれます。
●「部下が言い返さない文化」が根を張る
さらに厄介なのは、職場全体が
「上司に逆らうのはタブー」という
文化を持っている場合です。
組織の空気が“沈黙を強いる構造”を作り出しているのです。
心理的安全性の研究で知られる
エイミー・エドモンドソン氏は、
「チームの学習は、心理的安全性があるときにのみ起こる」と述べています。
つまり、意見を言い合える雰囲気がなければ、
成長も、改善も、信頼関係も生まれません。
結果として、ハラスメントが見過ごされ、
加害者も自覚できないままです。
■4.「正義」が暴走する心理
パワハラの根には、「正義の暴走」という心理があります。
“部下のため”“組織のため”という想いが強すぎると、
その目的のために手段を選ばなくなってしまうのです。
これは社会心理学でいう「道徳的免罪(moral licensing)」にも
近い現象です。
「自分は正しいことをしているから多少きつくても許される」
という心理が働くのです。
●事例:成績トップの店長の苦悩
以前、パチンコ業界のある店長研修で
こんなエピソードがありました。
ある店長は、売上トップの実力者。
しかし部下の離職率が高く、社内アンケートでは
「恐怖を感じる」と書かれていました。
本人は「数字を守るために必要な叱責だ」と言います。
「甘やかすとお客様に迷惑がかかる」と真剣です。
ところが、研修で動画フィードバックをした際、
自分の指導シーンを見て愕然としていました。
「こんなに怖い顔をしていたのか」
「自分がこんな声を出していたとは…」
他者視点に立つことで、
初めて“無自覚のパワハラ”に気づく。
これは非常に象徴的な事例です。
■5.「自覚」を促す第一歩は“他者の視点”
人は、自分の姿を自分では見られません。
だからこそ、他者のフィードバックが必要です。
- 360度評価
- 匿名アンケート
- 外部研修でのグループワーク
- コーチング面談
こうした“鏡”のような仕組みを通して、
自分の言動が他人にどう見られているかを知ることができます。
●「感情の可視化」がカギ
心理学者ダニエル・ゴールマンは、
著書『EQ こころの知能指数』でこう述べています。
「自己認識こそが、感情知能の出発点である」
つまり、怒りや苛立ちを感じた瞬間に
「今、自分は何を感じているのか?」と内省できる力が、
他者との関係を守る第一歩なのです。
たとえば次のようなアンガーマネジメント実践は効果的です。
- 怒りを感じたら6秒待つ(アンガーマネジメントの基本)
- 伝えたいことをメモに書き出し、冷静に整理する
- 感情と事実を分けて話す(「私は~と感じた」)
■6.職場全体で「気づける仕組み」をつくる
ハラスメントは個人の問題ではなく、
職場全体の構造的な問題です。
「誰も注意しない」「見て見ぬふりをする」「沈黙が安全」
という職場は、パワハラを“助長する温床”になります。
●仕組みの例
- ハラスメント相談窓口の設置(外部相談窓口の活用も有効)
- 匿名アンケートの定期実施
- 管理職研修でのロールプレイ・動画フィードバック
- 面談での「上司への逆フィードバック」制度
- 感情マネジメント・コミュニケーション研修の年次実施
特に外部研修では、社内では言えない意見が出やすく、
“気づきのきっかけ”が生まれやすくなります。
■7.まとめ:無自覚のパワハラは「誰でも起こりうる」
パワハラをしている本人が自覚できないのは、
単なる悪意の欠如ではありません。
それは、
- 「正義の思い込み」
- 「感情の鈍感さ」
- 「沈黙の誤解」
- 「過去の成功体験」
といった人間の心理的メカニズムが複雑に関わっているからです。
●自覚のない人を責めるのではなく、“気づける仕組み”を
「悪意がないのに起こるハラスメント」を防ぐためには、
個人を責めるのではなく、
気づける文化と仕組みを組織として整えることが大切です。
ハラスメント防止の目的は「加害者を処罰すること」ではなく、
「誰もが安心して働ける環境をつくること」。
そのために、心理的安全性と感情マネジメントの両輪で、
職場づくりを進めていきましょう。
■最後に
ハラスメントのない職場づくりは、一朝一夕では実現しません。
しかし、「気づき」が生まれた瞬間に、確実に変化が始まります。
もし職場で「自分はパワハラをしていない」と思う方がいたら、
それは悪いことではありません。
むしろ、そこから「どう見られているか」に目を向けるチャンスです。
さくら人材コンサルティングの研修サービスはコチラです!
さくら人材コンサルティング研修サービスコンテンツ
さくら人材コンサルティング株式会社
東京都港区浜松町2-2-15 ダイヤビル2F
営業時間:平日9時~18時
電話番号:03-6868-3248